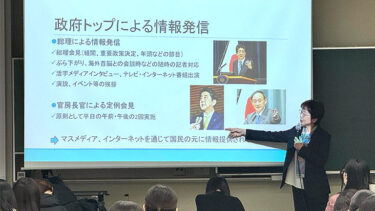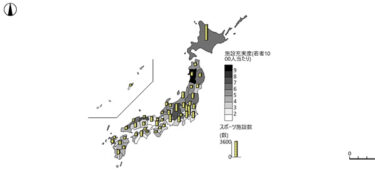現代教養学科3年の加藤愛歩と金内玲実です。6月14日、専門授業である「広告文化論(担当:見山謙一郎教授)」のゲスト講師として事業構想大学院大学の野口恭平教授をお招きし、マーケティングとブランディングについてのお話をいただきました。
野口先生は、現在、LIXILのマーケティングナレッジ開発リーダーをつとめられており、以前は日産で宣伝部長、北米日産商品企画室ダイレクター、グローバルマーケティング部長を経て、グローバルブランドコミュニケーション&CSR部長、ライセンスビジネス部長、知財プロモーション部長を歴任されていました。

講義では「マーケティングとブランディングの違い」についてお話しいただきました。マーケティングは「売れる戦略」、ブランディングは「売れ続ける戦略」であり、授業の前半でマーケティングの話、後半でブランディングの話をしていただきました。
<マーケティングとは何か?>
マーケティングのことを、広告やプロモーションのことだけだと思っている人は多いのではないでしょうか。しかし実際は「顧客にとっての価値を提供すること」という広い意味を持っています。商品・サービスの企画で重要なポイントは、誰に何を届けるのかを考え、自社製品の価値をいかに増幅させるかです。期待通りの商品か、値段は安ければいいのか、なにより顧客にとってのニーズに達しているかを常に意識し、高くても買いたいという価値を提供することが企業にとってのゴールと言えます。
私自身、マーケティングを企業のプロモーションのためだと思っていたので、実際は顧客に対するリスペクトであったことを知ることができたのは、今後の企業研究でも大きな力になると感じました。
そして、ニーズには「顕在ニーズ」と「潜在ニーズ」の二種類があります。顕在ニーズは、顧客側に欲しかったものという認識があるニーズ、潜在ニーズは、顧客自身は欲しいと認識していないニーズを指します。顕在ニーズは顧客も競合他社もわかっているため、同じ価値を提供するだけとなり結局は値段での勝負になってしまいます。そのため、いかに潜在ニーズに迫れるかがマーケティングの鍵になっているのです。
潜在ニーズは、顧客が無意識に欲しているものなので、企業がこれを把握するのはかなり難しいのだとお話を聞いていて感じました。いかに顧客に寄り添って考えるかが重要になるのだと理解できました。
また、競合他社の分析をする上で重要なのは、自社のポジショニングだというお話が個人的に印象に残っています。具体例としてサントリーのノンアルコールビール「オールフリー」のCM(2010年発売時)があげられました。この商品のはじめの価値は、アルコールゼロ・カロリーゼロ・糖質ゼロの「3つのゼロ」でした。しかし、顧客の求める価値は「ゼロ」ではなく、「ゼロがもたらす価値」と再分析した広告を出したことで、競合他社のノンアルコールビールよりも上回る売り上げを残しています。顧客にとってのベネフィットをクローズアップすることが重要と理解できる一例でした。
マーケティングをする上で重要なのは、顧客のニーズを完璧に理解することだと学ぶことができました。顧客と距離をとるのではなく、企業が顧客と近づいていく関係を築けることが重要なのかもしれません。私は現在3年生で、就職活動が目前に迫っています。企業のマーケティングにフォーカスした企業研究をしていなかったため、今後の企業研究ではこの授業で学んだことを生かしながら、自分の力にしていければと思います。(加藤)

<ブランドとは何か?ブランディングとは何か?>
講義を伺う前、私は「このブランドといえば○○」というイメージ戦略を思い浮かべていました。しかし、ブランディングとは単なるイメージ戦略に留まらず、あらゆる企業活動を通じて顧客が得られる体験価値によって作られていく総合的なものである、ということを今回の講義を通じて学びました。
今回はブランディングの施策として、ブランド戦略・ブランドを起点とした広告展開・ブランドポジショニングについてお話しいただきました。ここでは、それぞれの事例で特に印象的だった広告について紹介します。
ブランド戦略では、ディズニーの事例が印象的でした。ディズニーは「大人も子どもも笑顔にする魔法をかける」を価値として、ディズニー作品からパーク内のスタッフの様子まで、顧客に対して提供する一貫性を持っています。ディズニーしかないワクワク感はこのように作られているのだという点で強く印象に残っています。
次に、ブランドを起点とした広告展開では、Apple製品のCMが印象的でした。
Apple Watch・Air PodsのCMはブランドを通じた顧客体験が表現されていました。
以前目にしたことのある広告でしたが、今回の講義を通じて日常の利用シーンで製品がどのように活用できるのか、製品そのものではなく独自の機能性やデザイン性、顧客体験そのものを示していると新たに気づくことができ、興味深かったです。
最後に、ブランドポジショニングの事例では、「Dove」「Lux」で有名なユニリーバの「Dove Real Beauty Sketches」というスケッチを通して、自身が認識している自分よりも第三者に認識されている自分は美しいということを明らかにした実験動画のキャンペーンが印象的でした。この動画は「すべての女性が自分の美しさに気づき、自信に満ち溢れ、自分が美しいかどうかと悩まない世界を築く」ことをミッションとして掲げるDoveのブランドポジショニングを明確にしている点で、商品の宣伝だけが広告における戦略ではないという気付きを得ることができました。

今回の講義で紹介された数多くの事例を通じ、「マーケティングとは何か」、「ブランディングとは何か」について、各企業が「何のために」、「どのように自社の存在価値を伝えようとしているのか」ということを深く理解することができました。
売れ続ける仕組みづくりのブランディングのため、顧客にとっての意味や価値を持続性を意識しながら創造し提供していくこと。そして、時代や組織運営が変化していく中で、顧客にとって変わらない一貫したポジショニングで独自のブランド価値をつくり提供し続けることが重要だということを学びました。(金内)
野口先生、本当にありがとうございました!