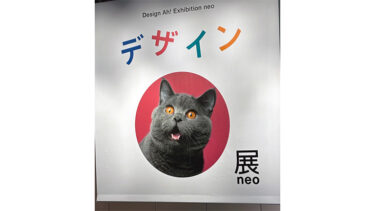こんにちは!現代教養学科の魅力を発信する学生広報メディアのCLA Reporters & Magazineに所属する現代教養学科2年の北村夏妃、新栄遥佳、宮林明莉です。
私たち3人は、4月16日(水)に開催されたCLA Reporters & Magazine(*1)と、CLA Creative Lab(*2) との共同企画「世界の医療団 ワークショップ」に参加しました。本記事ではその様子をお届けします!
今回のワークショップは、4月24日(木)から始まる「世界予防接種週間」に関連し、「私たちができること」を考えることを目的とし、第1部「国際NGOメドゥサン・デュ・モンド ジャポン(世界の医療団)の米良彰子事務局長のご講演」、第2部「現代教養学科3年 榎本紗希さん(世界の医療団 インターン生)司会による、クイズとディスカッション」という2部構成で行われました。当日は、現代教養学科の他、福祉社会学科や環境デザイン学科など学科や学年の違う10名の学生が参加し、活発な議論が行われました。

メドゥサン・デュ・モンド ジャポン(世界の医療団)は、フランスで始まった医療系の国際NGOで、紛争や自然災害、貧困、差別などで医療が受けられない人々に、将来にわたり医療を受けられるよう活動しています。世界17カ国に拠点を置き、70カ国以上でプロジェクトを実施し、日本にも拠点があります。(世界の医療団HP https://www.mdm.or.jp/)

当日講演をしてくださった米良さんは、大学卒業後、スポーツメーカーで海外営業として働く傍ら、阪神淡路大震災時に多言語放送局の立ち上げ・運営に携わられました。その後、アメリカの大学で国際関係学を学び修士号を取得されました。そして、国際機関でのインターンを経て、NGOで教育や保健、食料・栄養分野でのアドボカシー・キャンペーンに関わられ、バングラデシュ・ベナン・ブルキナファソ・ウガンダ・ネパール・インド・バヌアツなど様々な現場で国際協力に携わった後、2020年3月に世界の医療団の事務局長に就任されました。
米良さんのご経歴を伺い、国際協力の現場で実際にどのような経験が積み重ねられてきたのかを具体的に知ることができました。企業勤務からスタートし、国際機関やNGOでの実践に至るまで、一つひとつの選択が今の仕事につながっていることが伝わってきました。特に、アジアやアフリカ、太平洋の島国など多様な地域で活動されてきたことから、現場での経験を重ねながら道を切り拓いてこられたことに強い説得力を感じました。2020年から世界の医療団の事務局長を務めているというお話も含め、現場と組織をつなぐ立場としての責任と信念の強さが印象に残りました。
【第1部】 米良さんのご講演
「今日はなんの日?から考える今の課題」を題材に、正しい医療知識の重要性を教えていただきました。実際に、世界の医療団が活動されているラオスでは、医療の正しい知識がないことが課題だと言います。具体的には、予防接種の副反応に関する正しい知識がないため、「注射=即回復」という誤解が生じ、予防接種後の一時的な身体の不調を病気が悪化したように感じてしまう親が多くいたそうです。その結果として、予防接種を受けない人が増え、病気の蔓延や死亡率の上昇につながってしまうという課題を語ってくださいました。それらを防ぐためには、「正しい情報の伝え方」、「ファクトチェック」の二つが重要だとお話しいただきました。
このお話を通して、医療において「正しい知識」がいかに重要であるかを改めて実感しました。医療という命に関わる分野であっても、正しい情報が伝わらなければ、善意の選択が結果的に危険を生んでしまうことがあるというのは、とても重い事実だと思いました。また、予防接種のように本来「人を守る」ための行為が、誤解や不信によって避けられてしまう状況に、情報をどう届けるかという難しさも感じました。単に正しいことを言えば伝わるわけではなく、相手の立場や文化、背景を理解した上で伝える工夫が必要なのだと思いました。
そして、講演の最後にはNGOの存在意義は「課題を解決すること」にあり、世界の医療団の存在意義は「医療に繋がってない人を医療に繋げること」だとお話しされ、学生への期待として「世界の課題を自分ごとに捉えてほしい」と呼びかけられました。
【第2部】クイズとグループディスカッション

第2部では世界の医療団でインターンをしている現代教養学科3年榎本さんからNGOや医療に関して状況を知り関心を持つためのクイズが出されました。
多くのクイズの中から一問抜粋させていただきます。
- クイズ「世界初のワクチンである天然痘ワクチンが開発されたのはいつでしょう? 」
全体の半分は1946年と答えましたが、正解は予想の200年ほど前の1796年でした。
天然痘は人類史上、ワクチンによって唯一根絶することができたウイルス感染症でした。ワクチン開発から約200年後の1980年5月にWHOは天然痘の世界根絶を発表しました。
また、日本国内で初めてワクチンが製造されたのは1849年だといいます。
正直、そんな昔からワクチンがあったと思わなかったので200年以上前から存在していたにとても驚きました。
和気あいあいとした空気でクイズが行われ、新たな学びを得ることができました。
その後、榎本さんを中心に「私たちにできること」として「無関心を関心に変えるにはどうすればよいか」というテーマでグループディスカッションを行いました。ディスカッションでは2~4人のグループで、学年や学科の垣根を超えて活発な意見交換がされていました。

参加者からは、「ただ展示を見るだけでなく、自分も関われるような参加・体験型の展示にしたい」という意見が出ました。また、「Instagramのストーリー広告を使って、普段はあまり興味を持っていない人にもアプローチし、無関心を関心に変える工夫をしてはどうか」というアイデアもありました。
また、日本にいる私たちができることとして最初に思いつくことが「寄付」です。その寄付にはさまざまな方法があることも学びでした。例として、眠ってる本、DVDをチャリボン(不要になった本を寄付することで、寄付金としてNPOや社会貢献団体に支援を行うことができる仕組みを提供するサービス)を通して送ると寄付が出来るそうです。寄付というとお金のイメージが強いですが、お金以外にも自宅に眠る使わなくなったもので気軽に寄付が出来ることを学びました。このことは学内にも広めていきたいと思います。
ワークショップ終了後、この会を企画した榎本さんにお話を伺いました。
「私は3カ月、世界の医療団の米良さんがゲスト講師として登壇された「パブリック・リレーションズ」の授業をきっかけに、医療やNGOに関心を持ちました。実はこのワークショップ自体が、学生に世界の人道危機や課題について関心を持ってもらうために『私にできること』の一つでした。医療系の学生でなくとも、自分たちの学びや経験を通じて『誰もが治療を受けられる世界』の実現に貢献できることはたくさんあると思います。自分の学びと社会課題のつながりを考えることは、社会構想、多文化共創、メディア創造という三つの領域を学ぶ現代教養学科の学生の強みだと思います。」
様々な領域を学ぶことができる現代教養学科だからこそ開催できたワークショップであったと榎本さんのお話を伺いあらためて感じました。
〜ワークショップに参加した学生からの感想〜
- 「世界の医療団は自分が関わる分野ではないと思っていたが、ワークショップに参加して意外と身近にあるように感じた。今から自分でも取り組める事を考えていきたい。」
- 「現状を知り広めるそして問題を改善する、それを行っていく活動を応援していきたい」
今回、世界の医療団や医療の現状について初めて知ることばかりでした。自分にできる小さなことから世界へ、そしてその小さなことを周りに広める役割を果たせる社会人になりたいと思いました。そのためにできることを現代教養学科で学んでいきたいです。
*1 CLA Reporters & Magazineとは
学生が自分たちのメディアを創り、現代教養学科の魅力を伝えるための情報発信を行うプロジェクト。学科の行事や学生の様子などを取材し、冊子や動画など様々なメディアを作って情報発信をします。広報戦略の立て方や、メディアの特性を活かした企画作り、デザインの技法や動画表現の技法など、学科の授業等での学びを活かして、魅力的なメディアづくりを目指しています。
*2 CLA Creative Labとは
2024年度から始動した現代教養学科の新たなプロジェクト。①クリエイティブ・コンフィデンス、②マーケティング・コミュニケーション、③キャリアデザインという3つのテーマで現代教養学科の学生の可能性を広げていくための活動を展開しています。