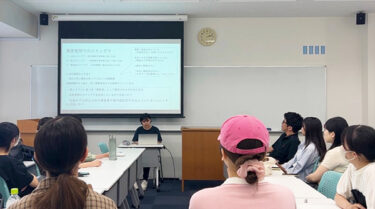こんにちは!比較文化論ゼミ3年の榎本、佐藤です。
今回は、7月23日にゼミの3年生で「高畑勲展ー日本のアニメーションを作った男ー」に行った様子をお届けします。


今回の展示会は高畑勲(1935〜2018)の生誕90年を記念し、スタジオジブリの企画協力を得て開催されたものです。『火垂るの墓』『おもひでぽろぽろ』などのスタジオジブリでの代表作の他にも、スタジオジブリで活動する以前の作品まで幅広く展示されており、日本のアニメーション文化の発展に貢献してきた監督の作品を深く知ることができました。
会場に入ると、『アニメーション映画で「思想」が語れるのだ。「思想」を「思想」として語るというより、物に託して語れる』という言葉が大きく掲げられていました。
監督デビュー作である『太陽の王子ホルスの大冒険』(1968)は、アイヌの伝承をモチーフに作られており、大量のスケッチからは監督のこだわりが感じられました。
その後の作品の『アルプスの少女ハイジ』(1974)『母をたずねて三千里』(1976) 『赤毛のアン』(1979)ではヨーロッパの街並みや生活様式が細かく描かれ、視聴者に海外文化への理解を促したと考えられます。
一方で、スタジオジブリの設立以降は『火垂るの墓』(1988)『平成狸合戦ぽんぽこ』(1994)などの作品を通じて、日本の風土や、庶民の生活に焦点をあてた作品を残しました。
晩年の作品では、日本の古典的な文化に再び価値を見いだす作品作りが特徴として挙げられます。『ホーホケキョとなりの山田君』(1999)では絵巻物の画法を採用し、遺作『かぐや姫の物語』(2013)では日本最古の文学作品を現代のアニメーションにアダプテーションしています。
このように高畑勲の作品を見ていくと、さまざまな文化をアニメーションに取り入れていることがわかります。アニメーションを通して、異文化への理解や文化の価値の再認識がされており、高畑勲の作品がその点において大きな影響を残しました。
また、海外からの観光客も多く、日本のアニメーション文化が世界中に受容されているのだと実感する機会となりました。
***
展示会後は、おいしいイタリアンをみんなで食べに行きました!