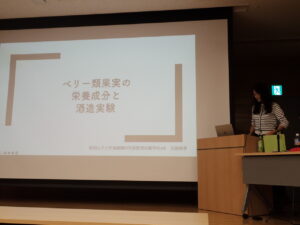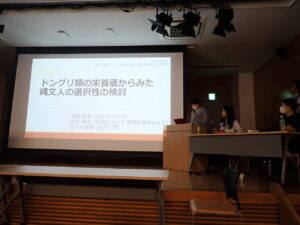本日ご紹介する卒業研究は、縄文食文化の研究する伊藤研究室です。
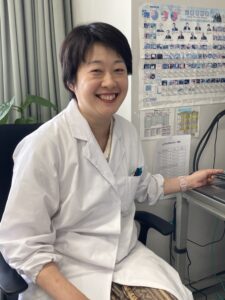 考古学と栄養学の接点
考古学と栄養学の接点伊藤研究室では、歴史文化学科の非常勤講師でもある植物考古学がご専門の金沢大学の佐々木由香先生と共同で、縄文食文化の新たな知見の追究をテーマに研究を行っています。縄文時代は、今から約1万6千年前を起源として、約1万3千年間続いた時代ですが、そのような古い時代でも、低地で水漬けになっていた遺跡(低湿地遺跡)からは、植物の種実などの有機物が酸素不足などの条件により微生物による分解を逃れて、植物遺体として数多く発掘されています。それによって、当時の植生や利用植物が明らかになってきましたが、考古学の領域においては、これらの植物遺体に関する栄養学的観点からの追究はあまり行われてきませんでした。そこで、植物遺体と同属・同種の現生の野生植物の成分分析などを通して、それらの植物が縄文時代になぜ選択され、どのような目的(栄養摂取?薬効目的?)で利用されていたのか、また、現在の栽培種と野生種とではどのような違いがあるのかを明らかにして、縄文人の食生活・食文化を考察するための一端を担えるデータの蓄積を目指しています。そのため、現生の野生植物を採集するフィールドワークも行っています。
公開座談会「縄文人 栄養足りてる?」
今回、東京都三鷹市生涯学習課が企画・運営した公開座談会「縄文人 栄養足りてる?」のお手伝いに行ってまいりました。メンバーは、縄文食文化の研究テーマで卒業研究を進めている3年生4人と4年生1名です。
本イベントは三鷹市の考古学体験講座で、ベースでは「考古学」ですが、座談会のテーマが「縄文人 栄養足りてる?-栄養学の観点から縄文食を検証する-」ということで、
実際に縄文時代の遺跡から発掘されている食材や調理器具(黒曜石製のナイフや砂岩製の石皿とすり石)を使用して、縄文食の復元調理実習をしました。
今回、東京都三鷹市生涯学習課が企画・運営した公開座談会「縄文人 栄養足りてる?」のお手伝いに行ってまいりました。メンバーは、縄文食文化の研究テーマで卒業研究を進めている3年生4人と4年生1名です。
本イベントは三鷹市の考古学体験講座で、ベースでは「考古学」ですが、座談会のテーマが「縄文人 栄養足りてる?-栄養学の観点から縄文食を検証する-」ということで、
実際に縄文時代の遺跡から発掘されている食材や調理器具(黒曜石製のナイフや砂岩製の石皿とすり石)を使用して、縄文食の復元調理実習をしました。
文献情報に基づき、ドングリのアク抜きが十分にされていたので、思いの外美味しいメニューになっていました。
座談会・研究発表会
午後には、座談会が開催され、4年生が卒業研究で取り組んだ縄文時代に利用が推定されるドングリ類やベリー類の粗タンパク量、粗脂肪量、水分、灰分の測定によって求めた結果と差引き方によって求めた炭水化物、それらをもとにAtwater係数から求めたエネルギー量などから、遺跡から数多く出土する特定のドングリがほかのドングリに比べて栄養価的にどのような違いがあるのか、また、植物遺体として多量の種子が出土している用途が不明のベリー類にはどのような栄養価の特徴があるのか、およびそれらベリー類を用いた酒造実験の結果についての発表を行いました。
このような研究活動を通じて、学生たちは、日本食品標準成分表に準じた成分分析法の原理ならびに技術を身に着けるとともに、古代から現代に続く食生活や食文化について、異分野の専門家との交流によって学際的な視点から考察する力を育んでいます。