〈日文便り〉
堀 誠 編『「古典探求」の漢文関連教材をめぐる実践と研究』(2025年3月)の第13章「災害詩と狂詩」を執筆しました。
https://www.gakubunsha.com/book/b659661.html
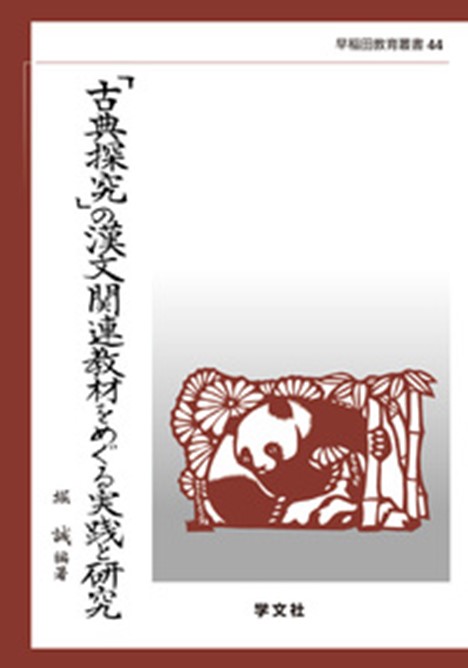
江戸時代に大きな災害が何度も発生したことは、みなさんご存じかと思います。当然、これらの災害を題材にした記録や文学作品も存在し、現代を生きる私たちにも重要な内容を含んでいます。ですが、これらの作品はあまり知られておらず、表舞台に出ることはなかなかありません。
そこで、今回の原稿では、小野湖山「乙卯十月二日都下大震小詩記事」を紹介しました。
小野湖山が遭遇したのは、江戸時代きっての巨大地震として知られる安政大地震でした。この大地震の経験を、湖山は真に迫る筆致で詠じていきます。形式は五言絶句で全13首ですが、今回は一部だけご紹介します。(※【】の数字は何首目にあたるかを意味します)
【1】
一震威何厲 驀然翻地軸(ひとたび震えて威 何ぞ厲しく 驀然として地軸を翻す)
家家皆倒催 人人尽號哭(家々皆倒れくだけ 人々尽く号哭す)
(訳)ひとたび地震が起こると、その威力はなんと激しいものか。大地を支える軸を急に翻したかのようだ。家々は全て倒されて壊れ、人々は皆号泣している。
【2】
震蕩勢未休 継以祝融怒(震蕩 勢ひ未だ休まずして 継ぐに祝融の怒りを以てす)
四顧皆炎烟 逃避竟無路(四顧皆炎烟となり 逃避するも竟に路無し)
(訳)地震の勢いはいまだ収まらず、祝融の怒り(=火事)をもって被害は継続する。
辺り一面は炎と煙に包まれ、逃げようとするも、とうとう逃げ場がない。
【1】では大地震発生の様子、【2】では地震後の火災が詠まれています。安政大地震の被害の大きさと人々が動揺する姿、そして、地震後に起こる火事の怖さが読み取れます。現代ほど消防設備が整っていなかった時代の大火事ですから、どれほど怖かったことでしょうか。なお、地震後の火事は恐ろしいもので、大正時代の関東大震災では、死者の9割が焼死とされています。
※「関東大震災100年」特設ページ、内閣府、2025年5月28日閲覧
https://www.bousai.go.jp/kantou100/
【7】
再震指時日 訛言東海翻(再震の時日を指し 訛言 東海を翻す)
人情懐危懼 昼夜遽驚奔(人情 危懼を懐き 昼夜遽に驚奔す)
(訳)再び地震が起きる日時を予言し、流言飛語が東海道中を騒がせる。人の心は危惧を抱き、昼夜を問わず、人々は慌ただしく驚き逃げ回る。
大きな災害が起こると、必ずと言っていいほど発生するのがデマ。湖山は地震後にデマが流れ、そのデマに右往左往する人々の様子も詠んでいます。現代でも、熊本大地震や東日本大震災が起こった際には様々なデマが流れ、多くの人々が慌てふためきました。悲しいことに、江戸時代でも現代でも「災害後にデマが流れ、そのデマに人々が振り回される」という構図が共通して見られるのです。
【13】
事極則生謀 禍轉便成福(事極まれば則ち謀を生じ 禍転ずれば便ち福と成る)
此理豈難知 君看剥輿復(此の理 豈知り難からんや 君看よ剥と復を)
(訳)事態が極限に達した時に謀を生かす。禍転じて福と成す。どうしてこの理屈を理解できないだろうか、いやきっと理解できるだろう。見よ、剥卦と復卦を(=見よ、再び復興する様子を)。
湖山は最後の13首目を復興への希望で結びます。反語表現が生む力強さは、地震に負けずに立ち上がろうとする強い意志や、湖山の復興への確信を感じさせます。
書籍に収められた原稿では、全首にわたって、白文に返り点を施し、訓読・語釈・現代語訳を附しました。災害の漢詩を扱うことで、災害時に起こりうる出来事を学んだり、防災意識を高めたりといった、国語教育から防災教育への展開可能性が生まれます。ご興味があれば、手にとっていただければ幸いです。
ちなみに、災害だけでなく、感染症を描いた日本古典文学もたくさん残されています。ロバート・キャンベル編著『日本古典と感染症』(KADOKAWA、2021年3月)がもっとも手に取りやすいでしょう。この本に私は関わっていませんが、あわせてお手にとってももらえればと思います。
https://www.kadokawa.co.jp/product/322005000659/
(荻原大地)

