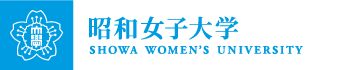MONTH
2010年12月
- 2010年12月20日
東明学林 今年のみかん
西洋美術史を担当しています木下亮です。 12月の初め、2年生と東明学林でみかんの収穫をしてきました。青空に映えるオレンジ色、枯葉を踏みしめるときの乾いた音、静寂のなかで時折あがる歓声。今年のみかんも美味しかった。このみかんの収穫は歴文の年中行事のよう […]
- 2010年12月18日
東明学林の雄大な景色
今年も残すところわずかになりましたが、いかがお過ごしですか。私たち歴史文化学科2年生は、12月1日~4日まで、小田原の郊外にある本学の宿舎「東明学林」に3泊4日の学寮研修に行ってきました。天候に恵まれ、病気になって寝込む学生もなく、無事研修を終えるこ […]
- 2010年12月2日
学寮研修が始まりました!
12/1(水)から歴史文化学科2年生対象の学寮研修が始まりました 今回は神奈川県にある本学施設「東明学林(とうめいがくりん)」で、3泊4日の研修を行います 写真は往路のバスハイクで参拝した鶴岡八幡宮です 2日目以降の様子についても後日アップしますので […]