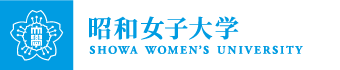現代教養学科では、毎年前期・後期と年2回特殊研究講座が開かれ、今学期(11月5日(水))の講師として迎えられたのは、日本で初めて性同一性障害者を公表のうえ東京都世田谷区区議会議員に当選し現在3期目を務める上川あやさんでした。
世の中には、性別といえば「男」と「女」の2種類しかないと考える人が多いのですが、実際にはそんなに単純なものではなく、生物学的な性別と自分の性別への自己意識が一致しない場合も少なくありません。そのような場合を性同一性障害といいます。
上川さんは元々政治家になるということなど思ってもいなかったとおっしゃっていました。政治家への道を歩んだきっかけは、自らが感じていた「日本という社会での生きづらさ」だったそうです。上川さんが区議員として立候補を決意した2003年当時、日本では戸籍上の性別変更が認められず、そのギャップはさまざまな場面で困難に直面しました。
その一例として、公的証明である健康保険証。上川さんは、外見は女性でも証明書では男性であったため、近所で噂が立つのを恐れて、風邪でも遠くの病院へ通ったそうです。また、ほかの公的書類の性別訂正制度もなかったゆえ、正規雇用も避けて仕事をしていたといいます。そんな過酷な状況のもとで、自ら声を上げて政治を変えるしかないとの思いに至ったそうです。
区議員になられた上川さんは、セクシュアル・マイノリティの問題にとどまらず、皆が住みやすい社会づくりを目指そうと、ほかのマイノリティ問題にも関心を寄せてきました。例えば、聴覚に障害がある方で手話を理解できるのは実は少数派という事実、点字ブロックの多くが規格外で形もバラバラだという事実、また大腸ガンに伴い肛門摘出手術を受けた方の通常トイレでの困難と苦労などなど…私たちの知らないところで困っている方がたくさんいらっしゃるのです。上川さんはそうした事実にも目を向け、これまでの行政がしてきたことを正し、いろいろ調べたうえでその改善策を実行に移してきました。
私が今回の講座で一番印象に残った言葉は、「常識」「当たり前」を鵜呑みにしないということです。今成り立っている社会で、「普通」はないのだと感じました。それは自分自身に関しても言えます。そして、あまり目を向けられていない人たちも理解して考えることが大事です。常識を疑い、声を上げてアクションを起こすことによって社会をより良いものにしていくこと、それが私たちの役目なのです。
年齢的には社会人と言われますが、私自身、社会に参加しているとあまり実感していません。しかし広くあるいは深く社会に目を向けると、実は社会に対する疑問があり、そこから社会づくりに参加できるのではと気づきました。
さまざまなエピソードに胸が熱くなった90分の講座でした。
(記事:シムゼミ3年・山本)